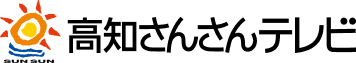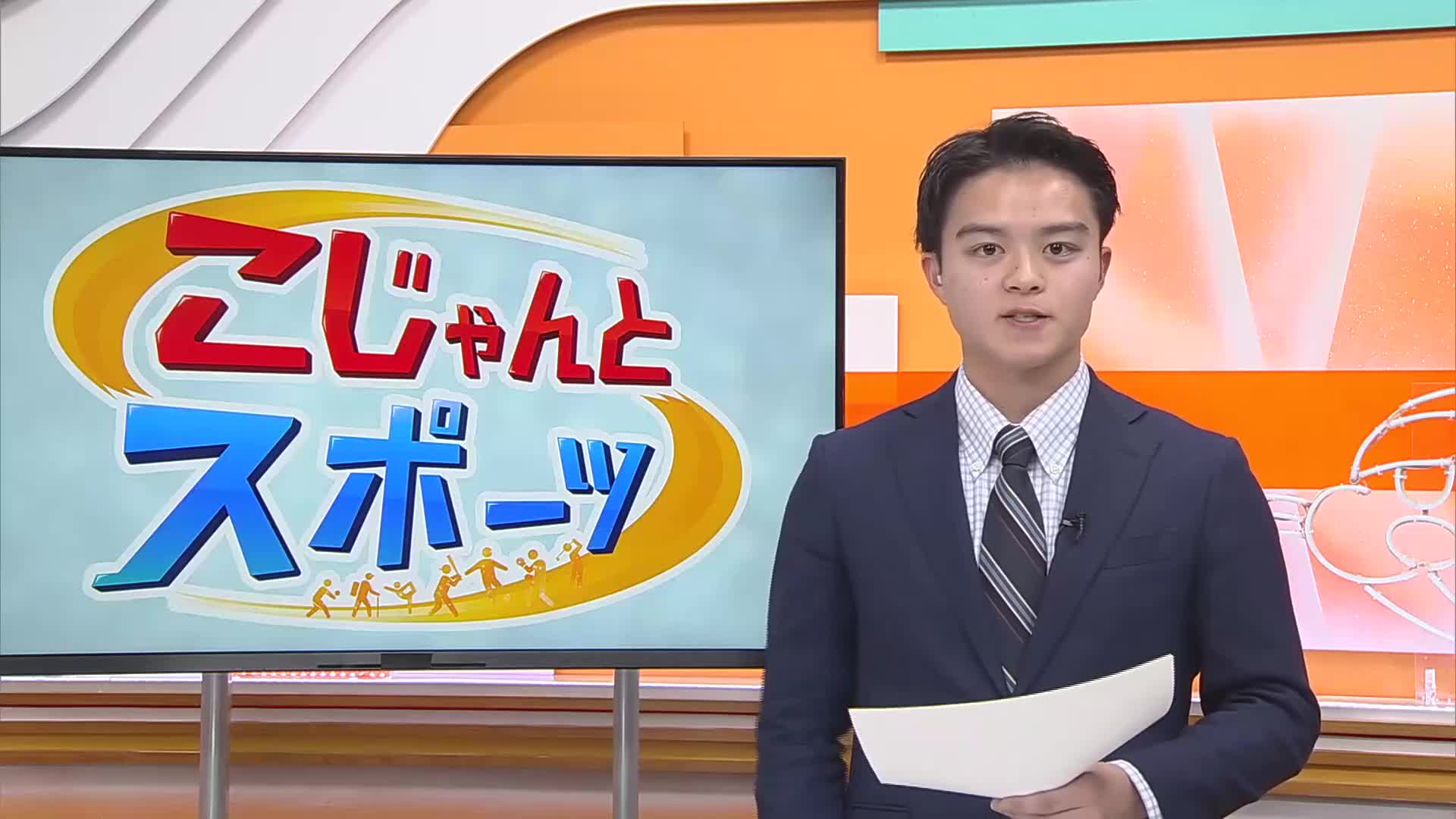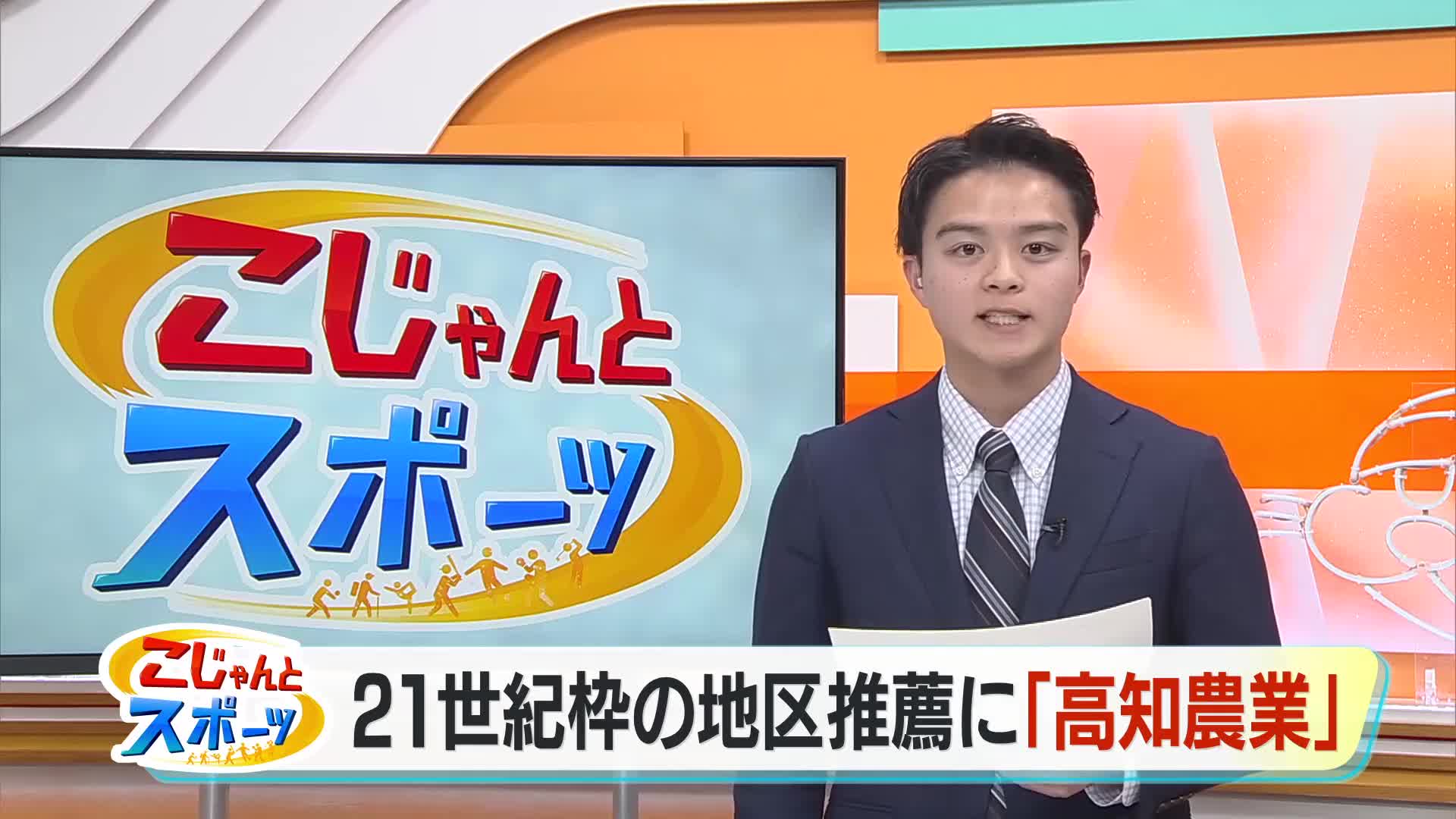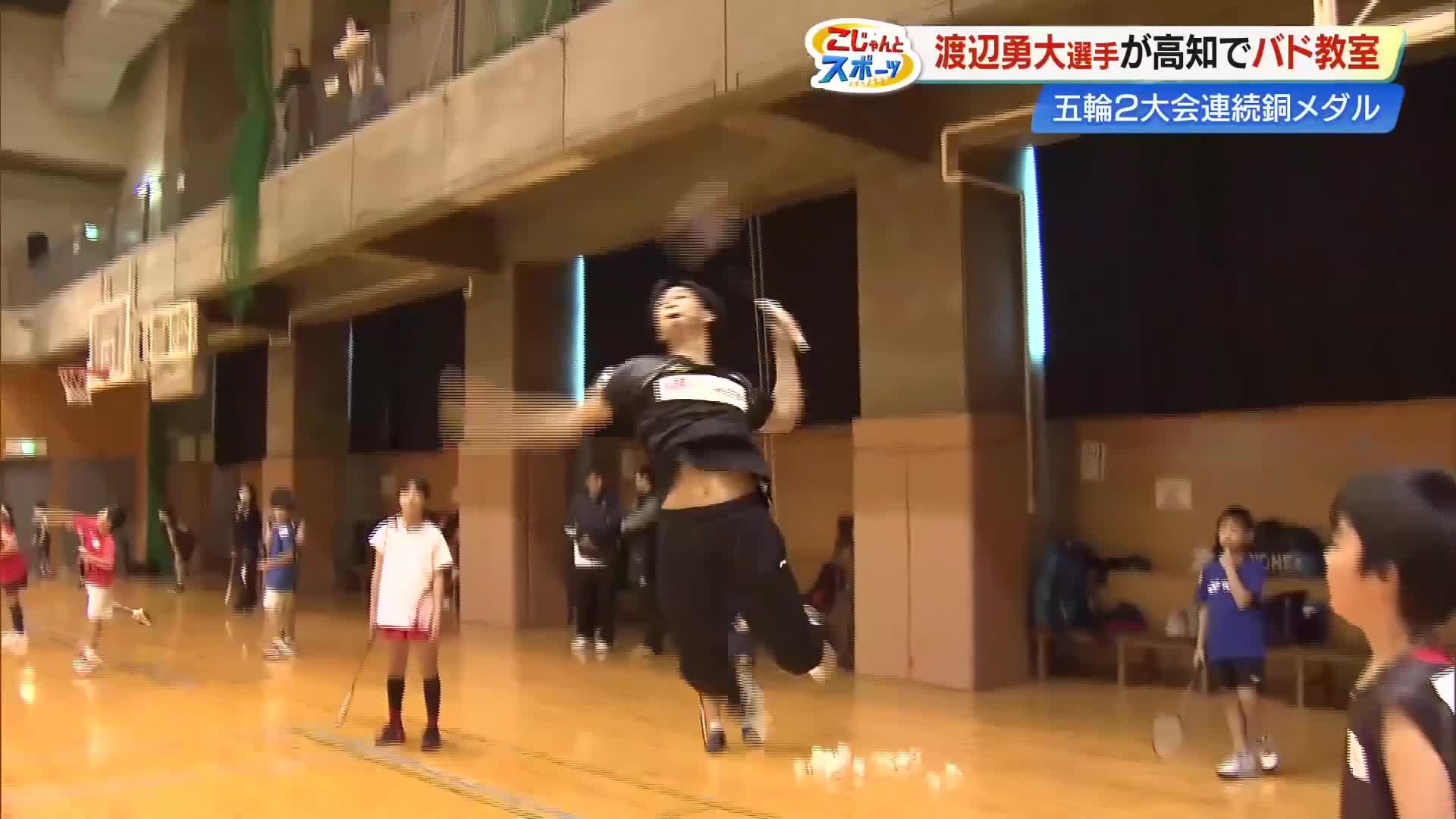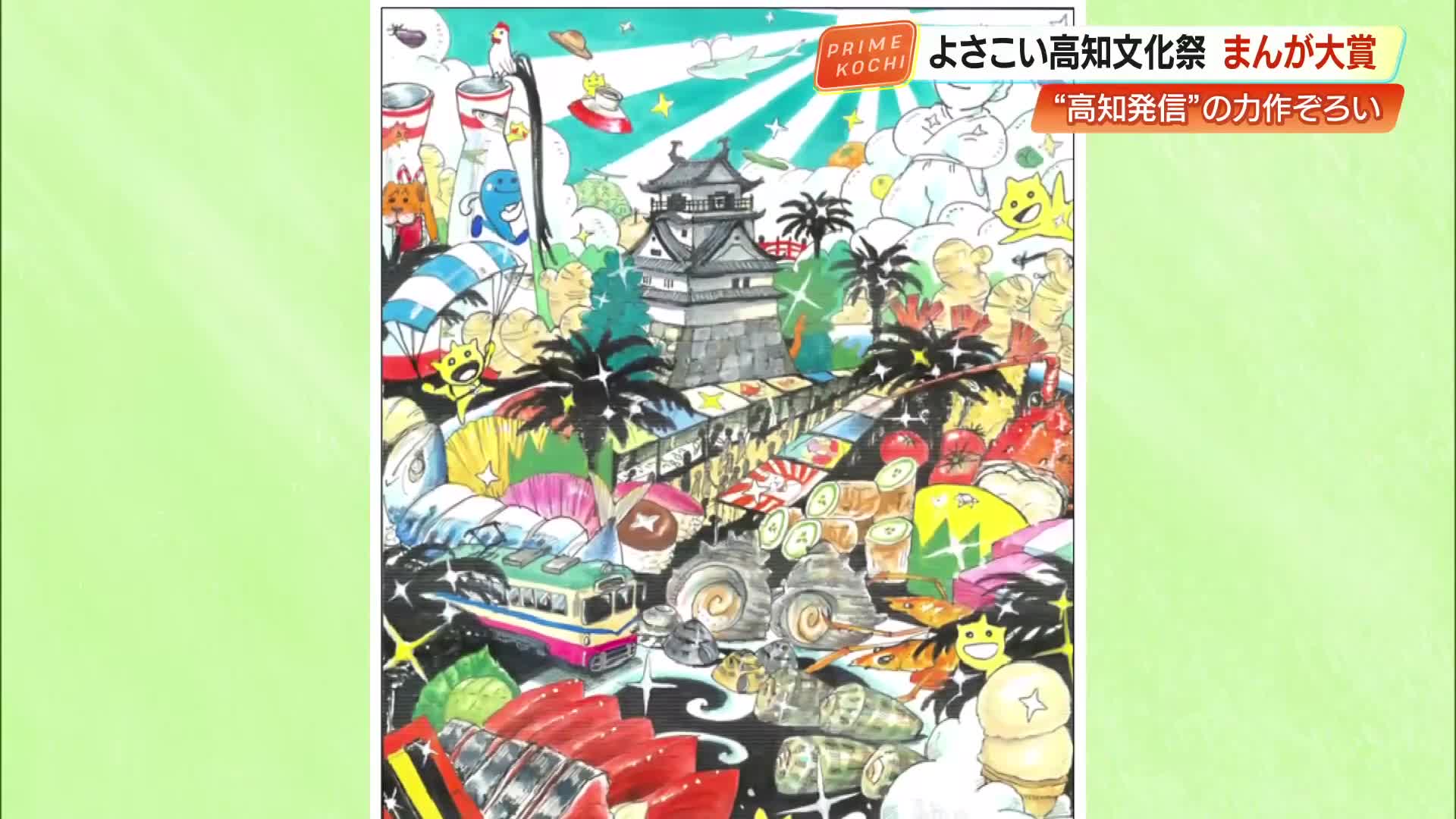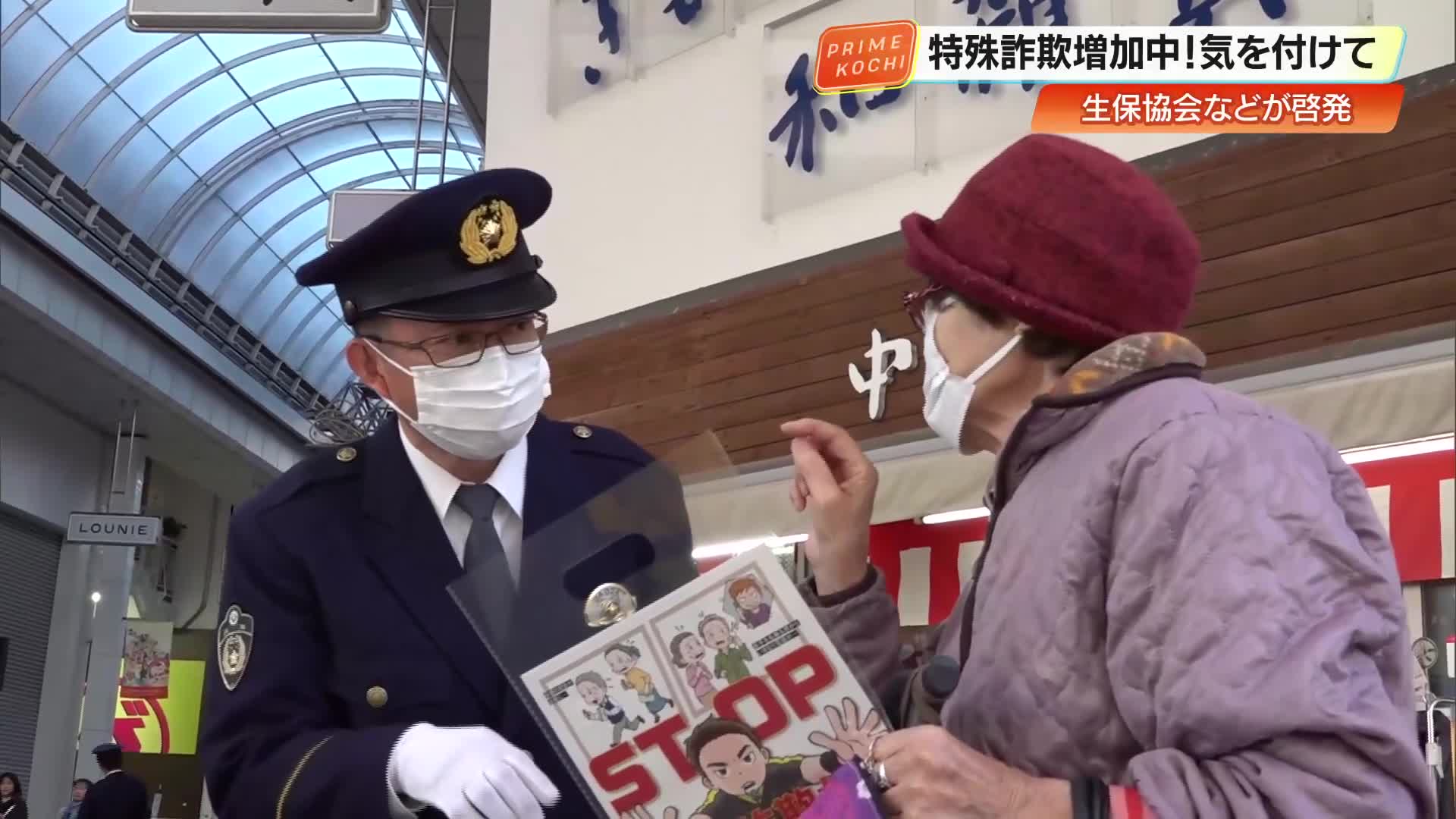拡大する高知の《防災産業》関西のバイヤーも「びっくり」亡き母のアドバイスで生まれた製品も
2024年2月27日(火) PM6時45分
能登半島地震の発生を受け防災意識が高まる中、高知の防災産業のすそ野が広がっています。
2月27日、高知市で行われた防災関連製品フォーラムには、県内18社の製品、約190点が並びました。能登半島地震を受けて県産業振興センターが急きょ開催を決めました。
安芸市から訪れた人は「きのう(2月26日)も地震がありましたし、ちょっと興味もあったので来ました」と話していました。
県が認定している県内企業の防災製品は年々増えていて、2021年度に初めて売り上げ100億円を突破、22年度には126億円を超えています。背景にあるのは、自分たちの技術や製品を防災に生かしたいという企業の意識の高まりです。
高知市の会社が開発した製品は――
(担当者説明)
「地震が起こるとLEDライトがついて誘導灯が点滅して。点滅することによって視認性をすごく上げているんです。遠くからでも避難場所が把握できるというところが一番の特長です」
避難所になる公民館などに設置しておけば、夜間に地震が起きても、どこに逃げればいいのかすぐにわかるという優れものです。
開発した島産業の本業は金属の卸ですが、新規ビジネスとして防災に取り組んでいます。牧野純社長は「南海トラフをはじめ、高知県が一番の(防災)先進県。少しでも県民の方含めて全国にこういうもので協力できることがあれば」と話していました。
おらんくの防災製品は、能登半島地震の被災者の役に立っています。災害用の浄水装置を開発しているアクアデザインシステム(高知市)は被災地で給水活動を続けています。
武田良輔社長は石川県からオンラインで参加し「十分な水のないことによって衛生環境悪化による感染症の発生が考えられるので“水”というのは本当に重要なことだと今回も改めて感じた」と現状を伝えていました。
高知市の化粧品メーカーが開発したのは、病気で人工こう門を付けている人のための防災トイレ。お腹から出した管から排便するため、通常の防災トイレでは無理な姿勢を取らないといけませんが、こちらの製品を使えば楽な姿勢で用を足せます。
開発をしたのはハンナ化粧品の中山聰子さん。母親が病気で人工こう門を付けたことで初めて、そうした人達が災害時にトイレで困ることに気付きました。
中山さんは「排せつってどんなことよりも我慢できないこと。より衛生的にということで防災に踏み切ることにした」と話していました。
関西から訪れていた防災製品のバイヤーは、高知の防災産業について「びっくりしました。防災とか避難という意識が非常に高い県であるということで、そういう企業がたくさんある。非常に驚きで、きょうは楽しみにして来ました」と話していました。
高知県防災関連製品フォーラムは高知市の「ちより街テラス」で2月28日も午前10時から午後4時まで開催されます。
人工こう門を付けた人のための防災トイレを開発した中山さんの母親は当事者としてアドバイスをしてくれたということです。今年1月に亡くなりましたが、同じ病気で困っている人の役に立つ防災トイレは「母親が残してくれた最大の財産」だと話していました。