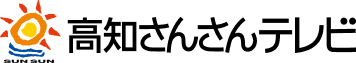『我々もただの使い捨て』5つの県立文化施設『公募』方針に波紋広がる 現場関係者が語る“不安”と“疑念”【高知】
2025年9月26日(金) PM6時04分
年間5万人以上が訪れる高知城歴史博物館、県立美術館、牧野植物園など5つの県立文化施設。その運営はこれまで、知事が外郭団体を指定するいわゆる「直指定」で行われてきました。しかし2025年6月県議会の総務委員会で、民間を含めて運営団体を“公募”する方針を示したのです。
浜田知事(8月8日):
「今の各団体の運営に、大きな不満があって変えたいと思ってるわけでは決してないんですけれども、今指定している団体以上にいい団体がないんだということを公募というプロセス、テストを通じて客観的に担保したいという思いであります」
現状の「直指定」では競争もなく、県立施設の運営権が与えられるかわりに各団体には、給与の上限や、管理代行料などから支出を引いた剰余金の返還など厳しい制約があり一定以上の利益が残らない仕組みになっています。そこで県は県立の5施設を“自律性向上団体”と位置づけ制約を大幅に撤廃。利益の使い方の自由度をあげて事業の創意工夫を促し給与アップを目指しているのです。
浜田知事(8月8日):
「本県の指定管理の施設はおおむね全国から見て求められる水準以上のサービスを実施してくれてると思ってますので、サービス向上に不断に努力をいただいていればそんなに心配をしていただく必要はないんじゃないかという感想を持っています」
税金を使う以上、公平性を担保するため公募の形を取るものの、管理団体が変わる可能性は低いと考えているようです。
県立美術館・学芸員 栁澤宏美さん:
「手を上げるところはないようなことをおっしゃいますけど、まだ募集要項だったり、どういった人たちが公募するところを決めるのかっていう材料がまだ何もわれわれの方には少なくとも提示されていない中で、ふたを開けてみたら他が手を上げてそこが取りそうだみたいなことになるっていう可能性は全然あり得るなというふうには思ってます」
贋作問題で揺れた県立美術館。それを逆手にとり収蔵作品を使って「本物とは何か」を考える企画展を開催し注目を集めています。県立美術館の学芸員、栁澤宏美さんは8年間、収蔵作品の管理や展覧会の企画を担当してきました。“文化施設”では“職員の努力と継続性”が重要であるはずなのに公募に突き進む県の考えに疑念を抱いたと言います。
県立美術館・学芸員 栁澤宏美さん:
「果たして今まで何を見て方針転換をされたのかなと。美術館開館して30周年以上経ってますけれども、それまでの積み重ねがあって今いろんな展覧会をやったり調査をやったり、そういったところに対応している。それは本当に(指定期間)5年とかで切れるものではないんですね」
西洋美術の仕事をしたいと県立美術館に入った埼玉出身の栁澤さん。今回の問題は学芸員など現場職員の確保に影響があると考えています。
県立美術館・学芸員 栁澤宏美さん:
「次の5年間どうなるかわからないとなると、私がもしそういった状態の美術館に遠方から(採用試験を)受けるとしたらやっぱりちょっと考える、一歩考えると思います」
5施設のうち最初に指定管理の期限を迎えるのが“城博”こと高知城歴史博物館です。土佐藩主・山内家の資料など約6万7千点を保存管理し魅力を発信する施設です。
県立高知城歴史博物館・渡部淳 館長:
「指定管理者制度はいろいろ課題が指摘されますけど、高知県の場合は『直指定』という形でスムーズにいった全国的にもお手本だった。それを『公募制』をということは、正直驚きました」
運営する「土佐山内記念財団」が山内家の宝物資料を保存管理する目的で設立された経緯を踏まえ県は9月議会直前に急きょ公募方針を転換。保存管理などはこれまで通り「直指定」で、事業の企画や施設管理のみ「公募」対象にする条例改正案を9月議会に提出しました。“公募”と“直指定”のハイブリッドについて渡部館長は。
県立高知城歴史博物館・渡部淳 館長:
「博物館というのは決して学芸員たちだけで動いてるわけではなくて、彼らがやった研究とかいろんな成果を広報していく。受付の皆さんも、どんどん変わっていく展示の内容をいつも勉強しててお客様に伝えていく。全員が情報を共有しながら、やっていく必要がある。できれば1つの組織として、やるのが1番の力を発揮できるんだろうなと思います」
県立文化施設の指定管理者を「公募」で選ぶという方針を示した県。きっかけになったのは牧野植物園の職員の処遇問題でした。2024年の2月議会で離職の多さに関する質問があり給与などの処遇改善が必要だとして県が検討を始めたのです。
Qこちらはどういう部屋?
牧野植物園・植物研究課長 藤川和美さん:
「ここは貼付した押し葉標本、先ほどの部屋で(やっていた)貼付した押し葉標本を半永久的に保管する標本庫です」
牧野植物園で、20年以上、植物研究に携わってきた藤川和美さん。これまで教育の普及や広報も担当し、牧野植物園での事業を多岐にわたって支えてきました。
牧野植物園・植物研究課長 藤川和美さん:
「学術標本を未来に残していこう。高知県の例えば植物、生物を保全保護しましょうっていう活動の中に、収益を上げる行為っていうのがないわけですよね。じゃ牧野でなんとか仮面のフェスティバルをやりましょうとか、場所貸ししましょうとか、そういうことをすることが本来の公益団体の目的ですかって思ったらやっぱり違うわけですよね」
歴代の研究員と職員たちが地道な作業を積み重ね、現在までに35万点もの標本がここに収蔵されています。
牧野植物園・植物研究課長 藤川和美さん:
「ここでの研究の価値は資料。それが高知県の財産であり、高知県に自然が残る活動をわれわれはしているわけですね。それに対する意義とか、お金では買えないものに関して自律性向上団体の指定っていうのがどういうふうになっているのかって不安な要素」
植物園としての意義を守りたいという藤川さん。今回の県の進め方を強い言葉で非難しました。
牧野植物園・植物研究課長 藤川和美さん:
「各館の例えば20年なりやってきた人間であったりそういう人間から何のヒアリングも今回受けないで(公募に方針転換)しましたよね。外郭団体の職員に対するこれ義理も礼儀もそういったものが一切ない。我々もただの使い捨てって、それで諦めてるんです私は。県に対して諦めた。県に対してです」
県が行った公募に対するパブリックコメントにも「文化施設に収益性を求める」ことへの反対意見、「職員の雇用不安」など300人、800件近くの意見が寄せられました。そんな声を受けて先週、博物館運営のプロや研究者、当事者など、県内外の有志が集まりよりよい文化施設のあり方や文化政策を考える議論の場を立ち上げました。
元県議会議員・大石宗さん:
「高知県の文化振興ビジョンの中に各文化施設についてこういう期待をするとか、こういう役割を求めるっていうことまで書き込んでないんですけれども、それも原因の1つじゃないかと思ってて」
元県議会議員の大石さんの問いに応えたのは文化政策の研究者、佐々木秀彦さんです。公募には文化施設の指針となる大きなビジョンが必須だと強調しました。
アーツカウンシル東京・佐々木秀彦 企画課長:
「まず文化政策があってこういうの目指すっていうのがあり、かつそれに基づいてそれぞれの施設にどういう期待があるかっていう、ことがあって、その期待に指定管理者はどう応えられるんだっていうことを提案してもらって選んでいくってことになるので、文化施設に将来何を期待するのかっていうことがないといい提案を出し合って競争をするっていう場がうまく成立しないんですよ」
高知の博物館や美術館が何を目的に、どんなことをやっていくか。大阪市立自然史博物館の佐久間大輔さんは直指定か公募かに関わらず現場の声を聞いた上で“文化施設のビジョンを作ることが重要”だと、力を込めます。
大阪市立自然史博物館・佐久間大輔 学芸課長:
「外部の有識者だけで作れる問題ではないし、現場を知らない役所の中の人たちだけで作れるものではないので、どう現場を関わらせる道を作るか、そのための準備をどうするかは非常に難しいけどやんなきゃいけないとこだなっていう風に思っています。博物館ってみんなでやんなきゃいけない所なので県庁と現場が乖離をしてしまうのが1番残念な事態なので、なんとかそれを回避できればなとは思っています」
9月19日(金)に開会した県議会。パブリックコメントや施設の声を受けて浜田知事は公募の内容変更について説明しました。
浜田知事:
「公募により指定管理者が変更となる場合、施設運営の専門性や継続性を確保するための措置が必要ではないかとのご意見もいただきました。公募にあたり現在勤務している職員の雇用の継続を条件づけるなどの手法により各施設等の実情に応じて対応することとします」
様々な波紋を呼んでいる県立文化施設の公募問題、現場の人たちの願いは。
牧野植物園・植物研究課長 藤川和美さん:
「お金が給与が良ければ、じゃあ人がここに残るかって言ったらそうではないと思うんです。研究と観光が今両立してるところなんだから次世代は教育普及やれみたいな(ビジョンが必要)」
県立美術館・学芸員 栁澤宏美さん:
「対話をしていく中で美術館や文化施設をどうしたいのかやっぱり現場の話を聞いて現場を見ていただきたい」
県立高知城歴史博物館・渡部淳 館長:
「最後は結局、県民にどれだけのサービスができるかとか、われわれがやった研究を県民にどれだけ還元できるかこれがおそらく行政もわれわれも共通した究極の目的だと思う」
文化施設のより良いあり方の模索のために。県と文化施設、そして県民も一緒になった丁寧な議論が求められています。