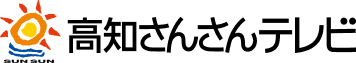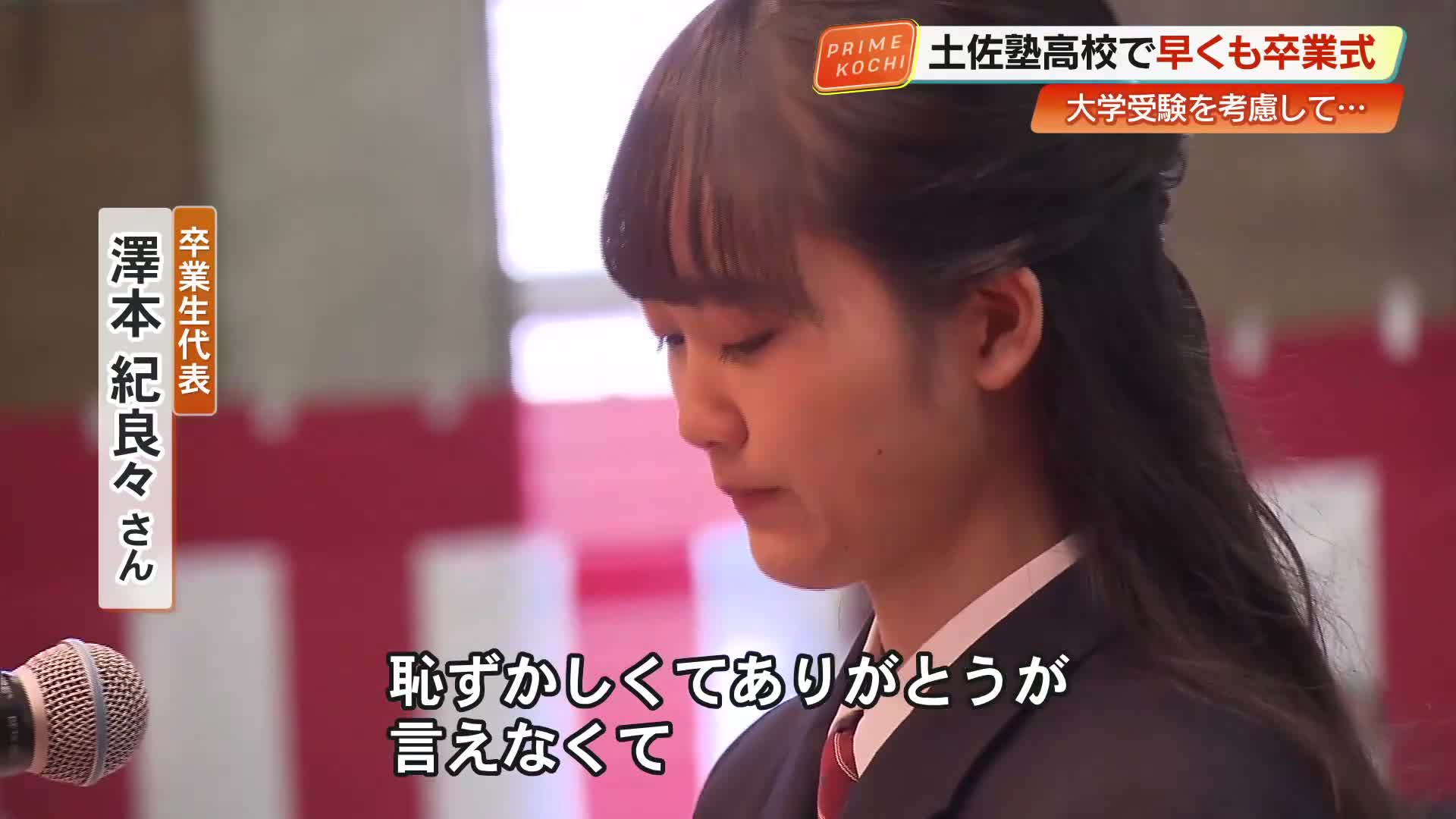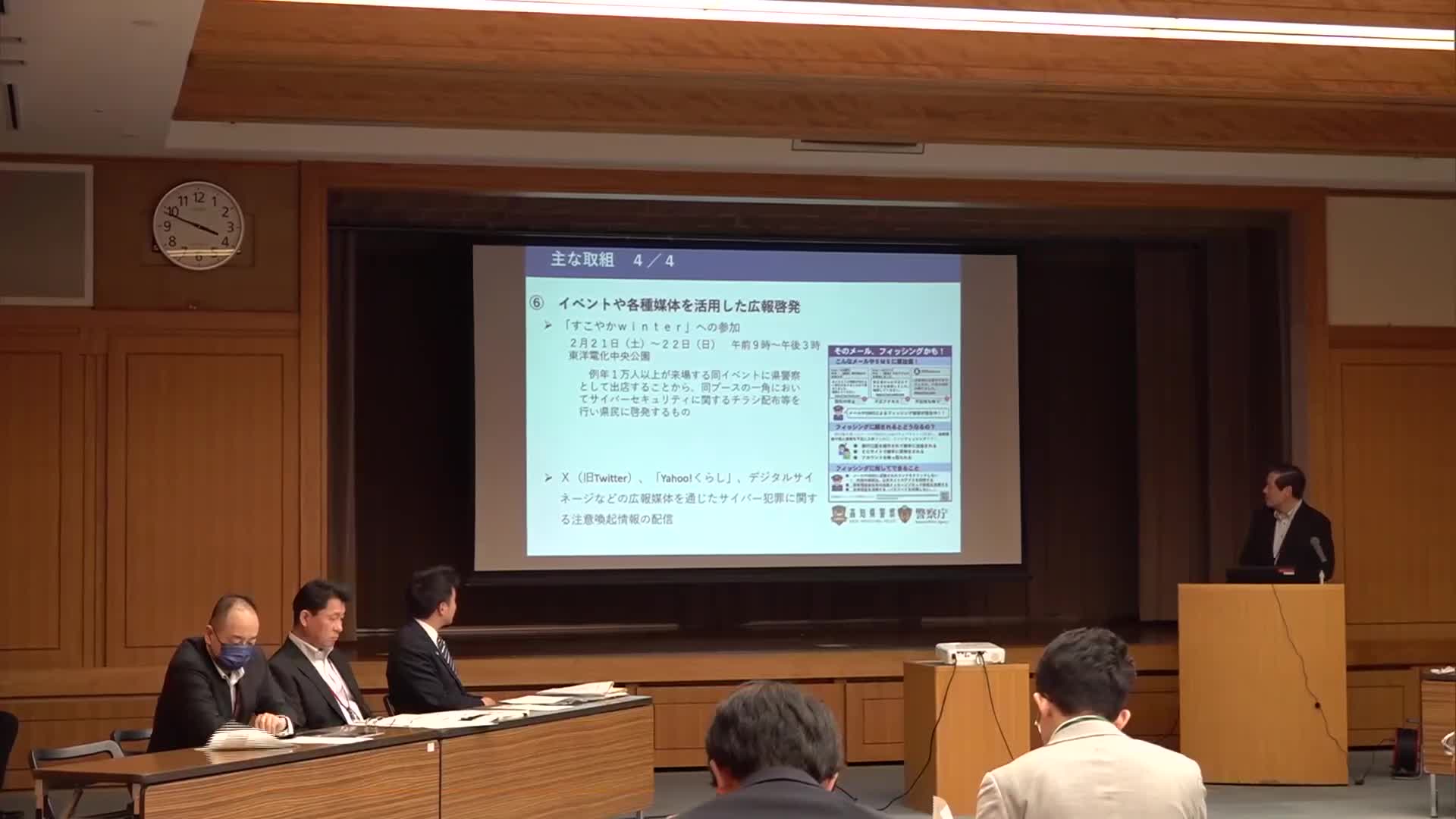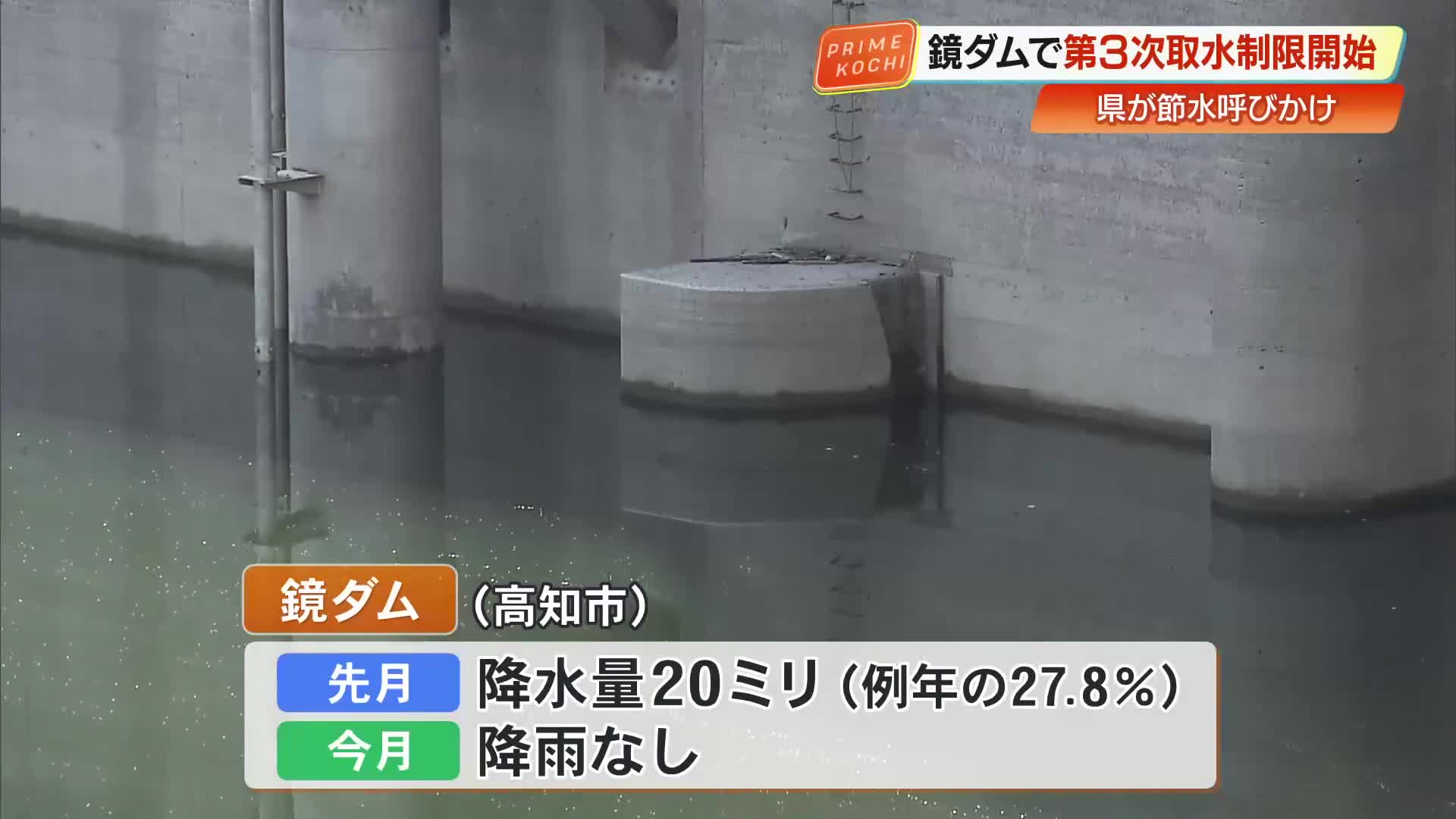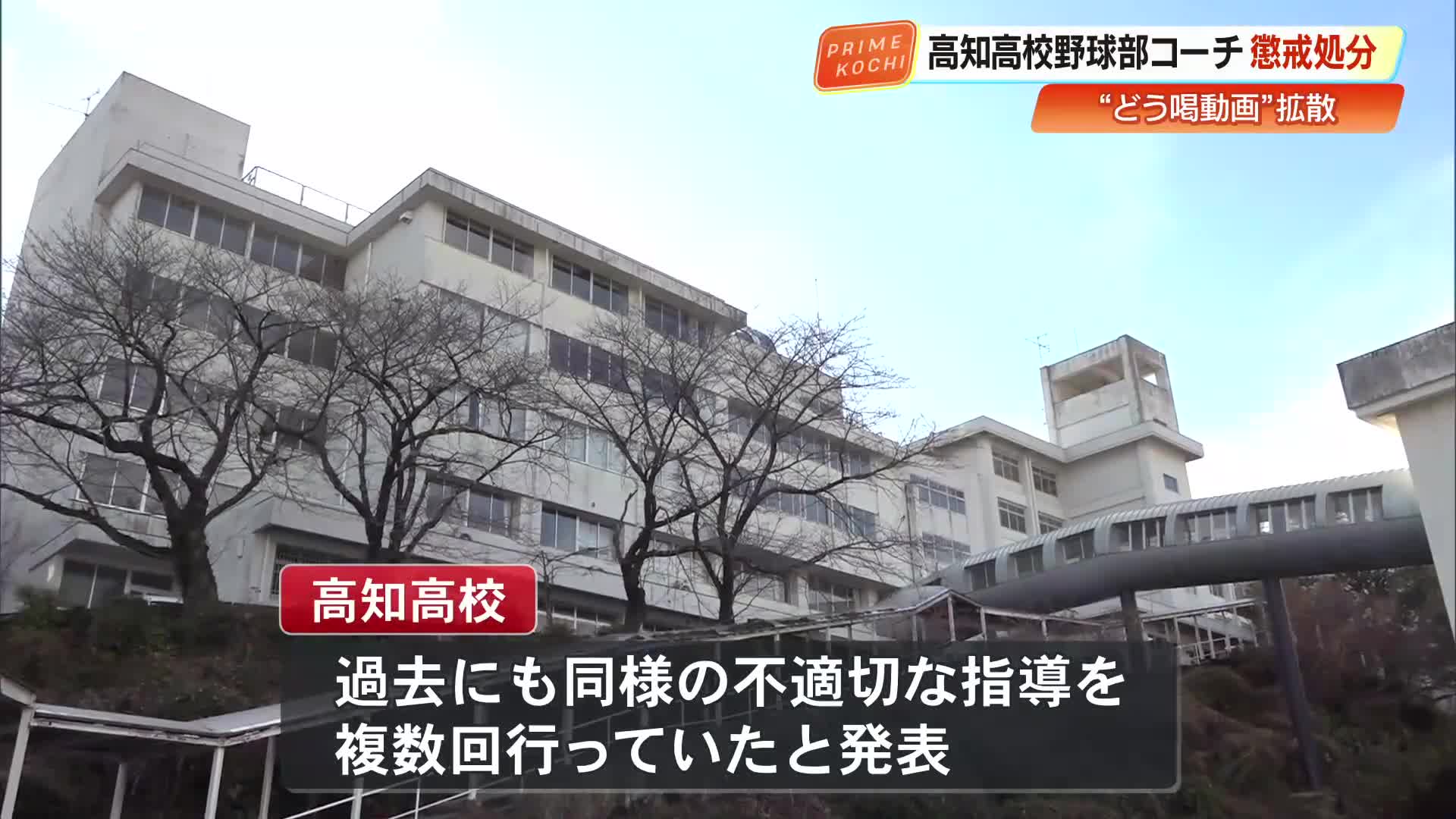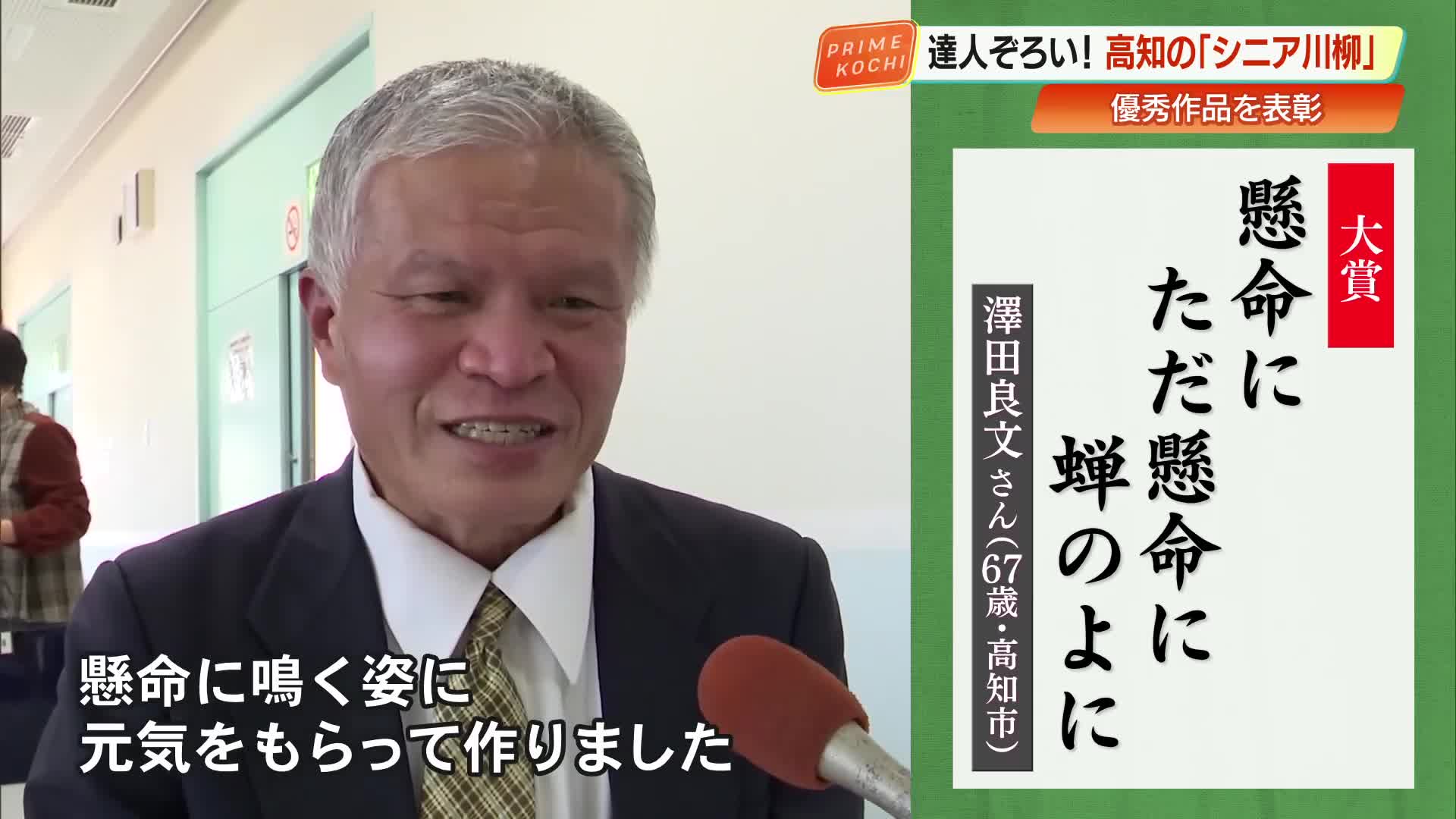宝永地震・種崎津波被害「亡所一草一木残ナシ」南海トラフ地震の歴史と教訓学ぶ「高知の地震災害史」展
2025年4月9日(水) PM7時55分 <PM8時13分 更新>
これまで幾度も高知県に甚大な被害を及ぼしてきた南海トラフ地震。その歴史や教訓を文献や写真などから伝える企画展が高知市で開かれています。
こちらは南海トラフ地震について確認できるもっとも古い文献で奈良時代に編さんされた日本書紀の記録です。684年に起きた白鳳地震による地盤沈降で土佐国に海水が流入している様子を伝えています。
高知城歴史博物館で開かれている企画展「高知の地震災害史」には主に江戸時代以降に高知を襲った3つの南海トラフ地震を伝える資料およそ100点が展示されています。
こちらは江戸時代1707年に起きた宝永地震に関する高知県の記録「谷陵記」。県沿岸部の津波被害の様子が記録されています。
高知城歴史博物館・水松啓太学芸員:
「例えばこの場所高知市の現在の種崎になりますけど、亡所一草一木残ナシと書かれておりまして、700人余りの人々が津波で亡くなったということが記されておりまして、津波被害の大きさがよくわかる記録になっています」
「谷陵記」の被害の記録を一覧で示したのがこちらの地図です。南海トラフ地震により地盤が隆起する地域と沈下する地域があるため被害に地域差が生じているのがわかります。
高知城歴史博物館・水松啓太学芸員:
「高知県の東部室戸岬なんかは南海トラフ地震が起こると地盤が隆起していきます。「谷陵記」の記録を見ると津波による被害が余りなかった。事ナシということで言葉が書かれています。一方地盤が下がっていく高知市中心部なんかは先ほどの種崎のように『亡所』と津波による被害が非常に甚大だったことがわかる」
中川記者:
「土佐市にやってきました。こちらは安政地震の4年後に建てられた石碑です。石の側面には津波の被害の状況や後世に向けた教訓が記されています」
石碑がある現在の土佐市宇佐町は幕末の安政地震でおよそ60人が津波で亡くなりました。
高知城歴史博物館・水松啓太学芸員:
「後代の変に逢う人必用意なくとも早く山の平らなる傍に岩なき所を択びて逃よかしと
書かれてありまして、早く高い場所へにげなさいということを教訓として伝えてくれています」
多くの人が石碑を目にするよう、遍路道の脇にたて、地域で語り継いだこともあり、後の昭和の南海地震では犠牲者が1人だったということです。
高知城歴史博物館・水松啓太学芸員:
「皆さんが暮らされている地域でどのような被害があったのか、そのことを知っていただいて、自らの防災対策に生かしていただけたらと思います」
この企画展は高知城歴史博物館で5月25日まで開かれています。