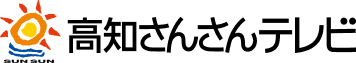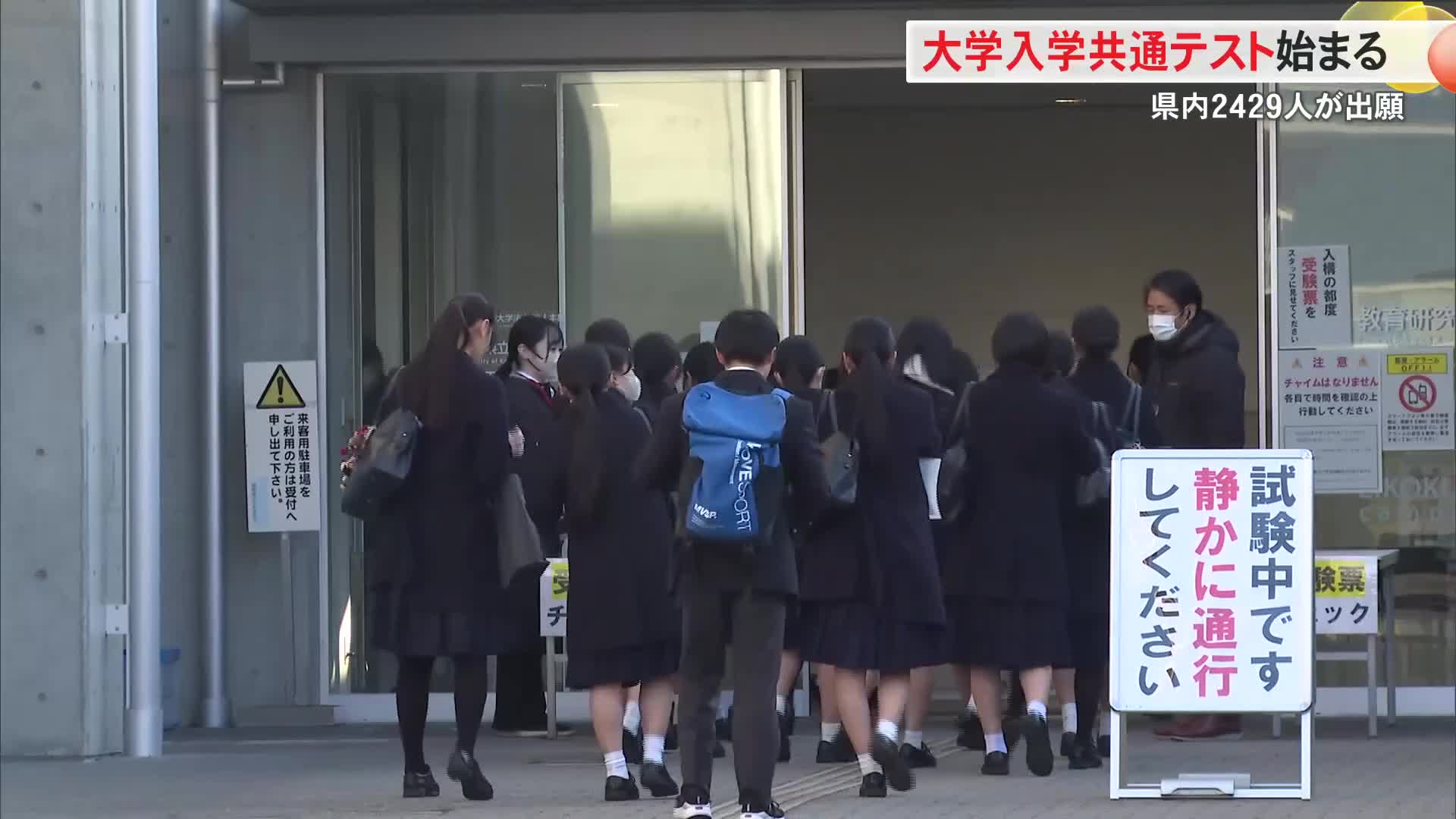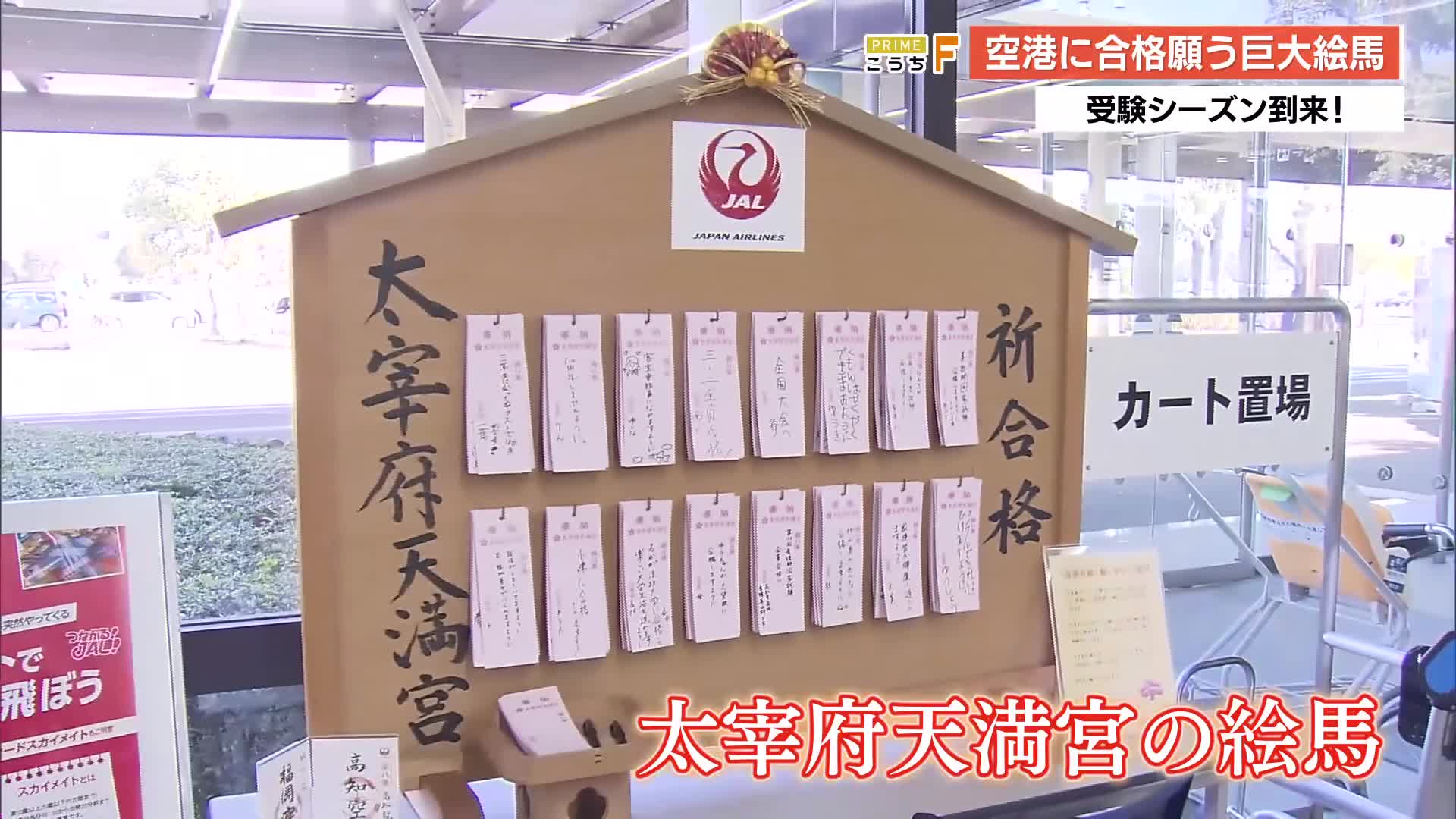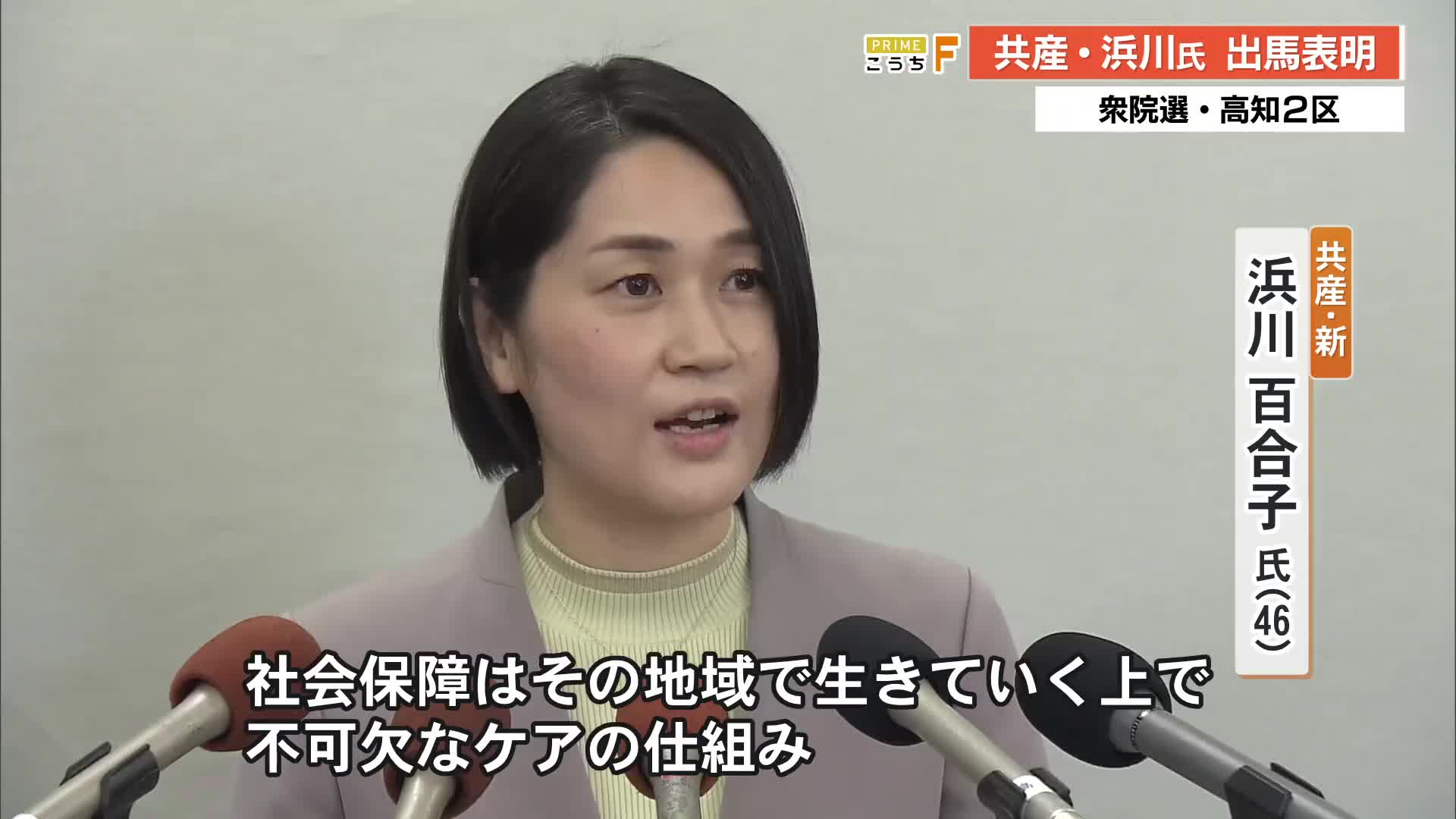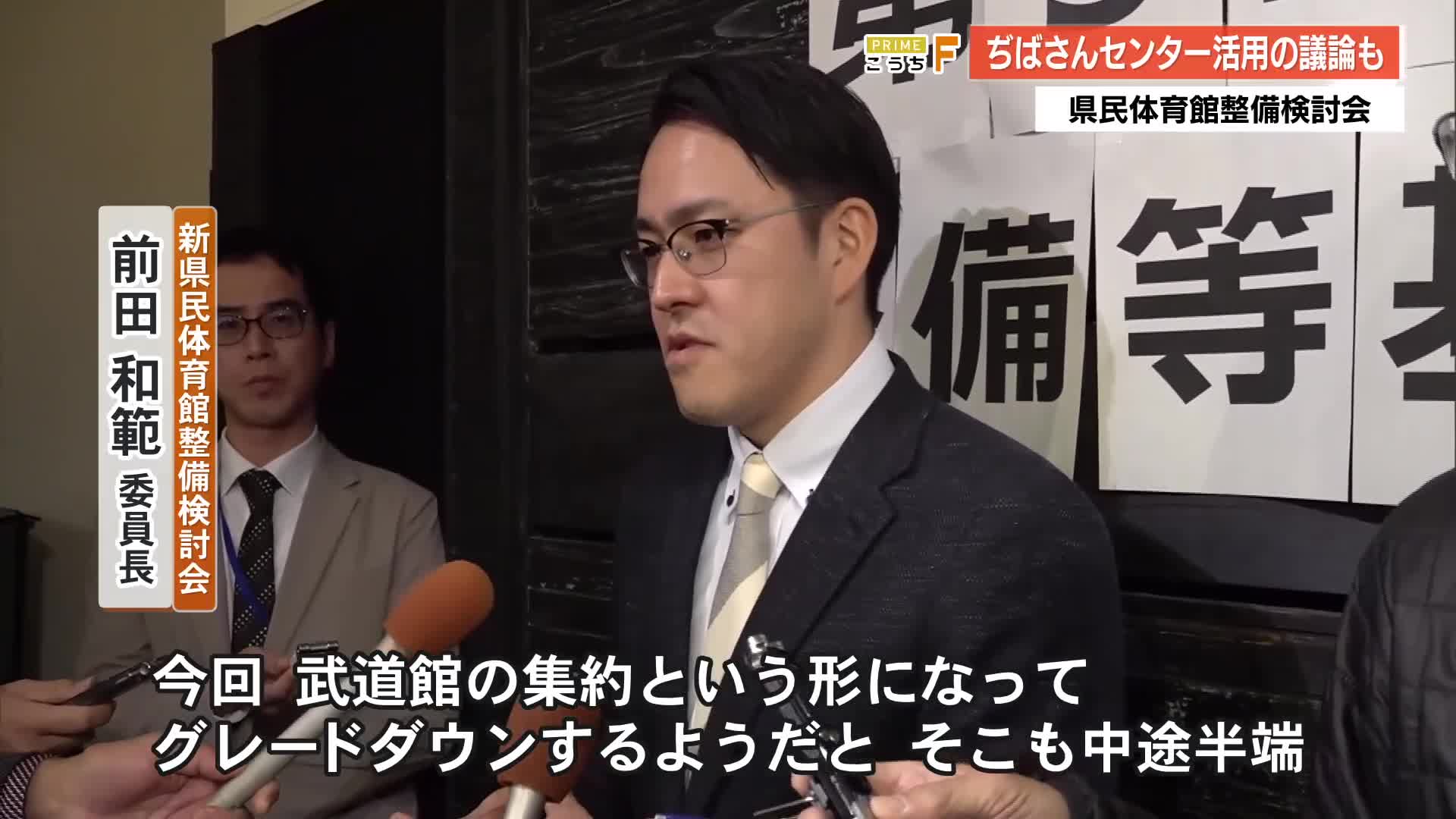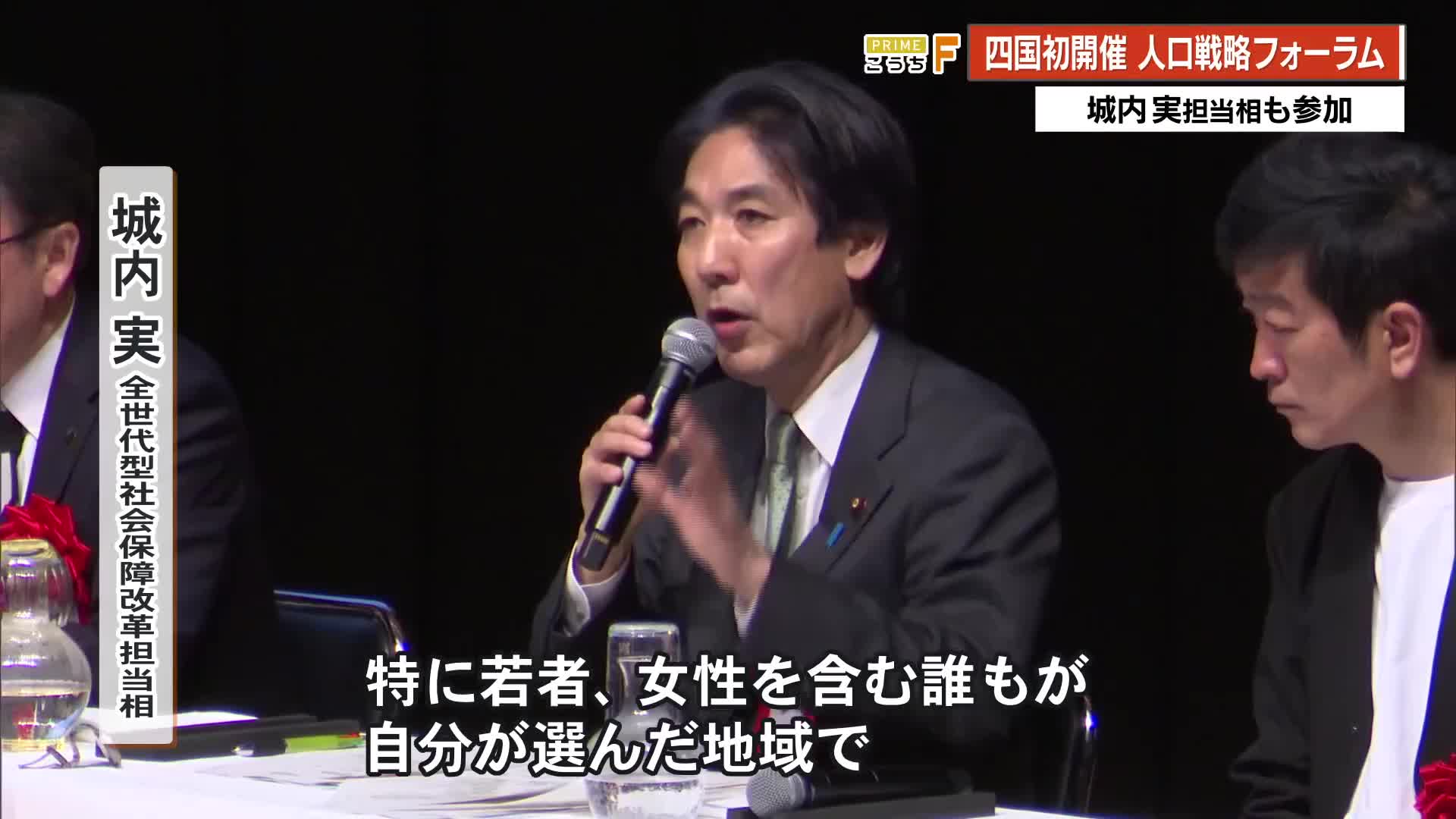四万十川で5年ぶり”アオノリ”収穫 海水温が影響
2025年1月24日(金) PM6時58分
清流・四万十川で5年ぶりに天然スジアオノリの収獲が始まっています。
緑の絹糸のような天然スジアオノリ。四万十川では2000年代およそ20トンを収穫していましたが、その後は不作が続き2020年から漁が途絶えていました。原因は川に流れ込む海水温の変化です。
スジアオノリの生態に詳しい高知大学・平岡雅規教授:
「アオノリは温度が高いと胞子を出して体がなくなって、低い温度だと自分の体を大きく育てる」
スジアオノリは水温が高いと自分の細胞を胞子に変えてしまい、糸状の組織を維持できなくなってしまうといいます。今シーズンは水温がノリの生育に適した15℃から20℃まで下がり、平均の40センチ程まで順調に育ちました。実に5年ぶりの収穫です。
川漁師:
Q.久しぶりに採れた感想は
「やっぱり楽しみが出るね」
川漁師たちは久しぶりの漁に喜びを隠しませんが平岡教授は楽観視していません。
スジアオノリの生態に詳しい高知大学・平岡雅規教授:
「また全然採れない可能性の方が高いと思います。黒潮の温度が世界平均の2倍ぐらい(の速さで)温暖化していて、高知県の海そのものが熱帯の生き物が増えてきているんですよ。この変化はちょっと止められないんじゃないかなと」
川で育つアオノリですが海水が入り込む汽水域に生息するため海水温が影響するといいます。5年ぶりに漁が復活した四万十川のスジアオノリ。順調に育てば2月も漁は続きますが、それでも収穫量は2トンほどの見込みで不作だったころの水準にとどまるということです。