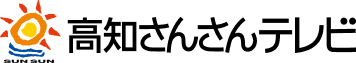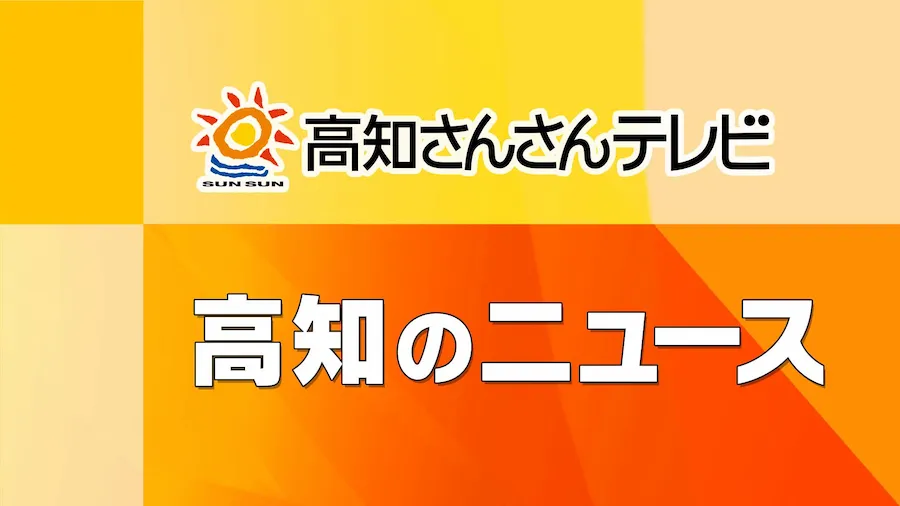南海トラフ地震への備え2「住宅倒壊による死亡者ゼロを目指したい」《命を守る耐震化を》【高知】
2025年1月15日(水) PM8時04分
阪神・淡路大震災から1月17日で30年です。過去の災害を教訓にして私たちが今取り組むべき防災とは?シリーズ『南海トラフ地震への備え』2日目のきょうは「揺れから身を守る耐震化」です。
1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災。死者6434人、犠牲者の多くが崩れた建物の下敷きになりました。
(資料映像 倒壊建物から救助)
「もうちょっと我慢して我慢して我慢して、もう一気にいってみて、もう思いっきり引っ張って、もう女の人入ってるんです2人。もうちょっと!もうちょい?あともう本当、足の所だけ」
揺れの長さは”15秒“でした。
耐震診断士・立道和男さん:
「地面がズズズズズって大きな音がして、それで突き上げられて本当に飛ばされたみたいに、ジャンプしたみたいになって、その後、回すような揺れでもう歩けない状態で」
高知県内で住宅の耐震診断を行っている立道和男さんは地震発生当時、大阪で工務店を営んでいました。自分が手がけた家に住む人から「家が倒壊してケガをした」と連絡を受けます。
耐震診断士・立道和男さん:
「隣の家の2階が自分のやった(建てた)建物の1階にのっているような状態。家に人が殺されるわけですからね。木造住宅のもろさっていうのかな。怖さっていうのもその時に実感して」
今後30年以内に70%~80%の確率で発生すると言われている南海トラフ地震。県は3分続く揺れや津波などで15万3千棟が全壊し、4万2千人が亡くなると想定しています。
そこで昭和56年5月31日以前に建てられた木造住宅に対し、耐震設計に最大44万2千円、改修に165万円の補助金を設けていて、昨年度実施した工事のうち半数が10万円未満の自己負担で済んでいます。
高知県南海トラフ地震対策課・伊藤孝課長:
「地震の揺れで住宅が倒壊することによって逃げられないということで、津波に飲み込まれる。そういったことも考えられますので、まずは住宅の耐震化をすることによって速やかに避難ができる態勢をとっていただきたい」
震災から5年後、両親の故郷高知に移住した立道さんは行政の補助金を使った低コストの耐震工事を請け負ってきました
去年12月、高知市の住宅で行われた改修工事では壁に揺れを吸収する装置「ダンパー」を取りつけていました。
耐震診断士・立道和男さん:
「筋交い、三角形のね。斜めになった材とか金物で、壁そのものの動きを固定してしまう。固めてしまうっていうのが耐震補強ですね。これが通常の工法で、ダンパーっていうのは通常の震度7が来た段階で20センチ本当は変形くるんだけど、ダンパーの方が戻そうとする力を働かすんでね。戻すことによって何回かの地震に耐えることができる。命は助かったけど帰れない家じゃ困るので、帰れる家を目指そうよっていうことで今、これをすすめていますね」
県内の耐震化率は89%。特に高齢者が一人で暮らす家は改修工事が進んでいません。立道さんは「子どもや孫からも声かけを行ってほしい」と呼びかけています。
耐震診断士・立道和男さん:
「(阪神・淡路大震災から)30年経った今は次の世代にどうつないでいくか、というところに来ている。自分の家だけじゃなくて、隣近所みんなで力を合わせて、みんなが防災に強い街づくり、家づくりをやっていってもらいたいと。住宅の倒壊による死亡者ゼロっていう形を目指したい」
県によりますと去年4月から11月末までの補助金の申請件数は前年度の同じ時期と比べて1.5倍に増えているということです。