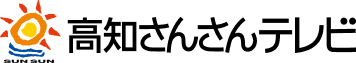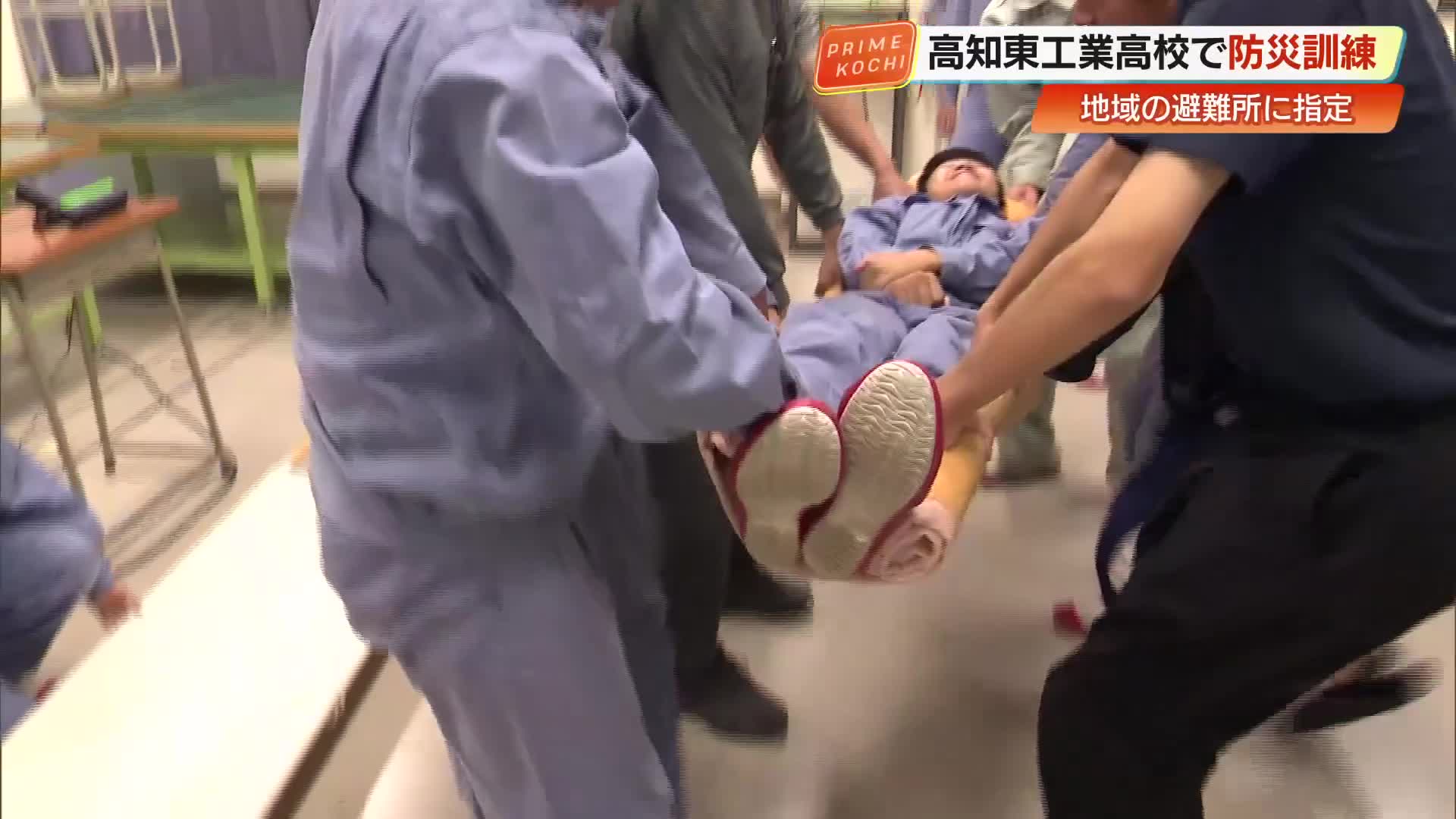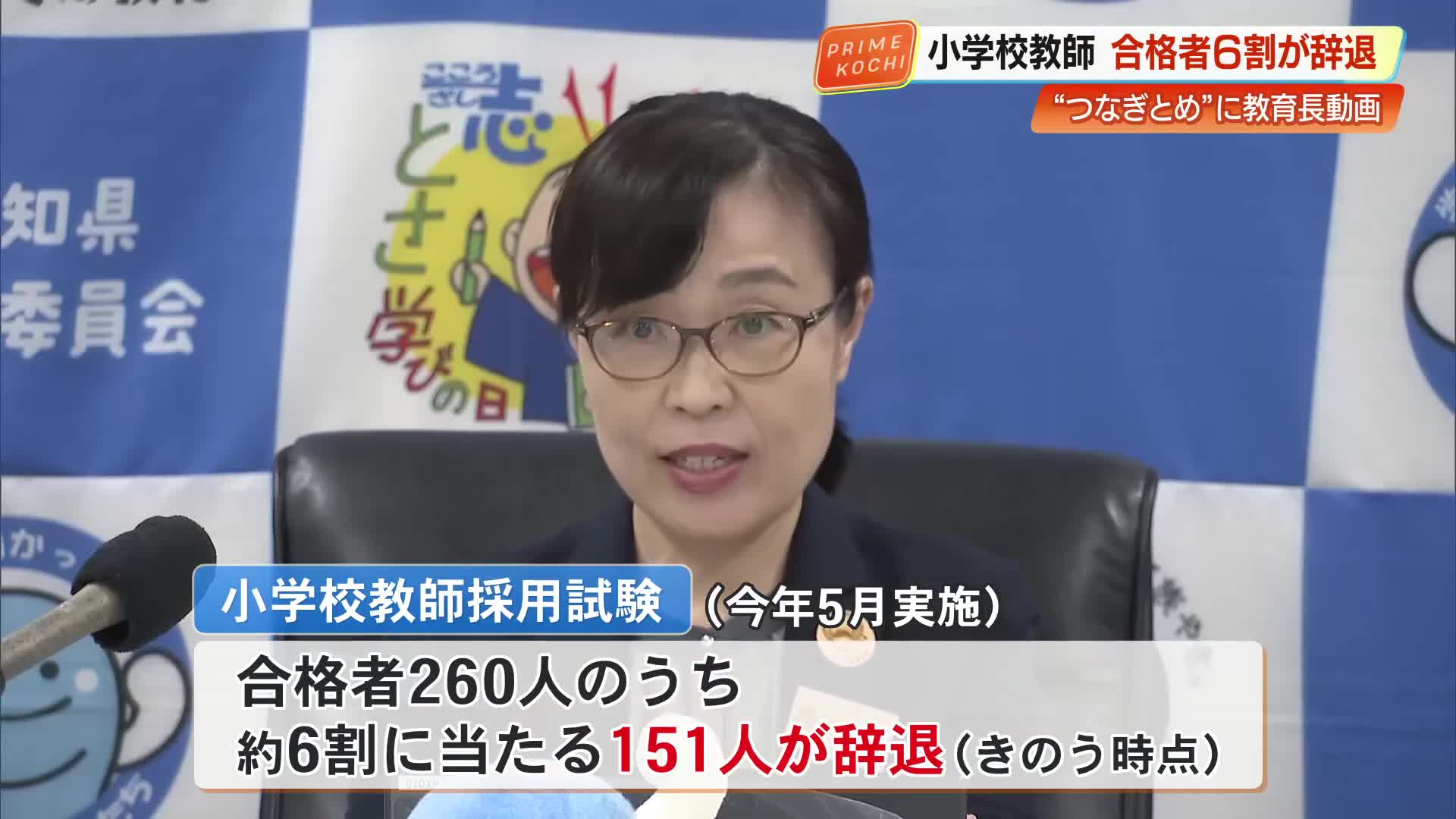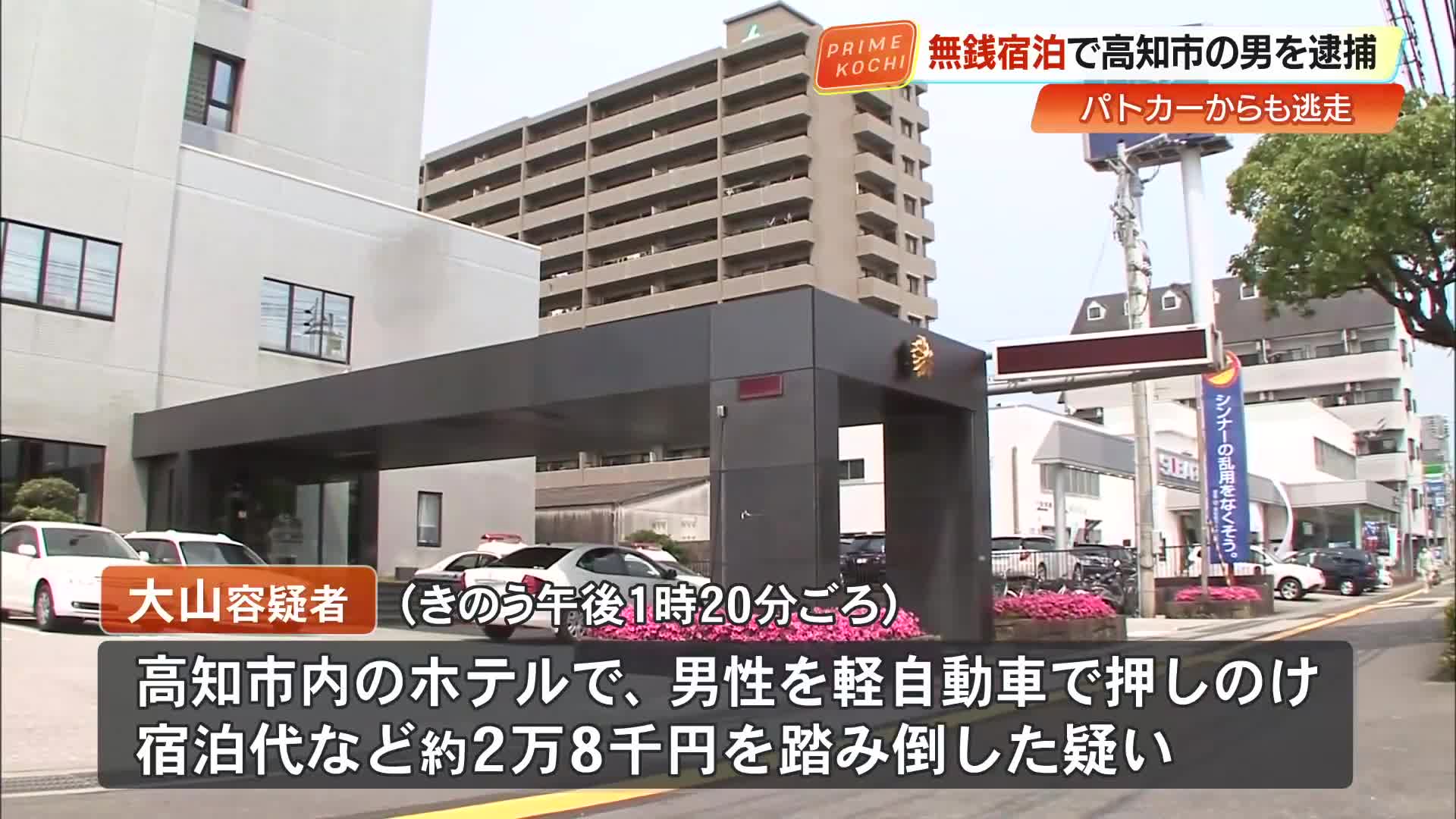食虫植物はなぜ虫を食べるのか?ムジナモ赤ちゃんも展示@牧野植物園【高知】
2024年7月26日(金) PM7時40分 <7月27日 PM4時18分 更新>
「食虫植物」ってどうして虫を食べるのか、ご存じですか?
食虫植物の仕組みや成長過程がわかるイベントが、高知県立牧野植物園で行われています。2024年初公開の赤ちゃん”にも注目です。
県立牧野植物園で行われている「食虫植物展」。ハエトリグサや、県出身の植物学者・牧野富太郎博士が学名を付けた食虫植物など、約60種類・150株が展示されています。
本来、植物は根っこを通して土などから養分をとりますが、食虫植物は湿った荒野や湿原など養分の少ない環境で育つものが多いため、虫からも栄養を補充します。
「ネペンテス・トルンカタ」は、においで虫をおびき寄せるウツボカズラの仲間。虫を捕まえる「捕虫袋」は長さ30センチ以上と世界最大級で、虫だけでなく小型のネズミやトカゲも捕まえるそうです。
ミジンコやボウフラを捕まえる「ムジナモ」の“赤ちゃん”もいます。7月上旬に発芽したばかりで、大きさは約1センチ!よく見ると、苗の下にまだ種がくっついているのが分かります。
東京から:
「かわいらしい、ちゃんと種があってそこから少し(苗が)出てて。いろんな方法で虫を捕まえて自分が生存していくために。自然界の神秘を感じました」
ムジナモは1890年に牧野博士が東京都江戸川区の用水池で発見し和名を付けました。花や種などを描いた細かい植物図は残されていますが、発芽した苗は描かれていません。園によりますと国内の植物園で初芽が確認されたのは初めて。
植物展ではムジナモの発芽直後の写真や発芽までの栽培過程などを解説したパネルも展示されています。
牧野植物園・丹羽誠一さん:
「種から発芽した苗、こういう風にムジナモは成長していくという過程をみなさんに見ていただきたい。植物の多様性を食虫植物で感じていただいて、特にお子さんにはこの面白い植物を夏休みの自由研究の題材にしていただければ」
食虫植物展は9月1日まで。28日にはハエトリグサに虫を与える体験イベントも行われます。